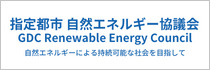太陽光発電の世界の導入量は2022年に過去最高の243GWを記録し、累積導入量は1,185GWに達しました。国際エネルギー機関は更に急速な拡大を予測しており、2030年代には毎年800GW以上が導入され、2050年には世界全体の電力の41%が太陽光発電で供給されると予測しています。拡大の最大の理由は発電コストの劇的な低下です。こうした世界の動向に反し、日本での毎年の導入量は減少傾向にあります。しかし、世界に比して割高だった太陽光発電コストも、2023年末には1kWhあたり8円を切る案件も出てきています。ルーフトップや耕作放棄地の活用などで、導入拡大を進めることが重要な課題です。
太陽光発電の世界の導入量は2022年に過去最高の243GWを記録し、累積導入量は1,185GWに達しました。国際エネルギー機関は更に急速な拡大を予測しており、2030年代には毎年800GW以上が導入され、2050年には世界全体の電力の41%が太陽光発電で供給されると予測しています。拡大の最大の理由は発電コストの劇的な低下です。こうした世界の動向に反し、日本での毎年の導入量は減少傾向にあります。しかし、世界に比して割高だった太陽光発電コストも、2023年末には1kWhあたり8円を切る案件も出てきています。ルーフトップや耕作放棄地の活用などで、導入拡大を進めることが重要な課題です。