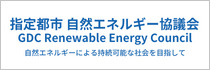今回のエネルギー基本計画改正において、本来、経済産業省がめざしていたのは、2030年のエネルギーミックスを見直すとともに、昨年10月に宣言された2050年カーボンニュートラルを実現することのできるエネルギー需給の構造を描くことであった。このため計画案を検討する基本政策分科会では、2050年への脱炭素化戦略の議論にも多くの時間がさかれ、私たち自然エネルギー財団も含めいくつかの機関からのシナリオが報告された。
しかし、9月3日に経済産業省が開始したパブリックコメントに付された計画案は、この課題に応えたものには全くなっていない。公表された計画案は、2050年までの「不確実性」と「不透明性」を繰り返し、ひたすら「複数シナリオの重要性」を強調するにとどまっている。奇妙なのは、「複数シナリオの重要性」といいながら、計画案が複数どころか一つのシナリオも提示できていないことだ。
2050年までの未来に不確定性があるのは当然だが、世界の大勢となっているのは2030年までに電力の半分程度あるいはそれ以上を自然エネルギーで供給し、2050年に向けては熱や燃料を含む、ほとんど全てのエネルギーを自然エネルギー由来のグリーン水素やグリーン合成燃料で供給するという戦略である。
計画案はEUが複数のシナリオを提示していることを、自らの「複数シナリオ論」の根拠としている。しかし、EUの示す8つのシナリオは全て自然エネルギーで電力の8割以上を供給することを前提とし、火力発電は2~6%を占めるにすぎない。国際エネルギー機関が本年5月に公表した2050年戦略では自然エネルギーが電力の88%を供給し、CCS火力は3%にすぎない。
更に、本年8月に米国エネルギー省が公表した報告書では、2050年に自然エネルギー電力が95%を供給する脱炭素シナリオを示している。残りの5%は原子力であり、化石燃料による火力発電はゼロである。これはまだ調査報告書であり、米国政府の正式な計画ではないが、こうしたシナリオがエネルギー省から公表されることは、米国でも自然エネルギーを中心にした脱炭素化が検討されていることを示唆している。
自然エネルギー財団が本年3月に公表した「脱炭素の日本への自然エネルギー100%戦略」は、日本においても自然エネルギーを中心とした脱炭素化が可能であることを実証的に明らかにした。
世界は、不確定性がある中でも、自然エネルギーがエネルギー供給の圧倒的に大きな部分を占めることは確定的な未来としてとらえ、これを前提にした複数のシナリオを描いているのである。
計画案は、「再生可能エネルギーについては、主力電源として最優先の原則の下で最大限の導入に取り組」むと書きながら、CCSの利用を根拠に化石燃料発電の継続をもくろみ、原子力発電についても「必要な規模を持続的に活用していく」としている。なぜ、経済産業省は、欧米、国際機関で打ち出されているような自然エネルギーが電力の9割前後を供給するシナリオを描こうとしないのか。
昨年秋からの改正プロセスの中で、当初、経済産業省は、2050年においても、電力供給の中で自然エネルギーの割合を50~60%にとどめ、原子力発電とCCS付火力発電で30~40%を供給するというシナリオを提案していた。しかしこのシナリオは、今回の計画案に盛り込まれていない。
その背景には、経済産業省が根拠として引用していた英国の事例が誤りであることが判明した1ことや、経済産業省の依頼を受けた地球環境産業技術研究機構(RITE)のシミュレーションへの批判が相次いだことがある。
RITEのシミュレーションは、2050年においても発電部門や産業部門で大量の化石燃料を使い続けけることを前提としたものであり、日本で発生する2億トン以上の二酸化炭素を毎年、海外に輸出するという驚くべき内容を含んだものであった。
基本計画案は、その冒頭で「今後の気候変動問題への取組は、産業革命以降形成されてきた産業構造を一変させる可能性を秘めるものであり、変化への対応を誤れば、産業競争力を失いかねな い。」と述べている。この認識は正しいが、懸念すべきは、まさに今回の計画案が、自然エネルギーが中心となる未来を描かず、ますます高コスト化する化石燃料と原子力を使い続ける方向を選択することによって、日本経済の未来を損なう危うさをはらんでいることである。
エネルギー基本計画は、世界の標準的な脱炭素戦略と同様に、そして日本でも実現可能であることを当財団が実証したように、自然エネルギーを中心とする2050年シナリオを提起すべきである。こうした明確なシナリオを示すことによって、企業のビジネスや投資戦略を的確に誘導することが可能になる。
- 1経済産業省は、2020年12月25日に策定した「グリーン成長戦略」の中で、再エネ比率を「世界最大規模の洋上風力を有する英国の意欲的なシナリオでも約65%」と記述し、日本の2050年における再エネ目標を5~6割とすることの根拠の一つとしていた。しかし、この数値は英国政府の目標ではなく政府が設置した気候変動委員会の2019年の報告書の数字であり、2020年12月9日に公表されていた新しい報告書では、2050 年の変動型自然エネルギー電力割合を 80%とし 85%、90%という代替シナリオも提示していた。