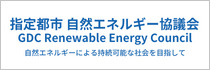2021年1月25日、欧州委員会の共同研究センター(Joint Research Center:JRC)が、森林由来の木質バイオエネルギーの気候変動への効果を分析する報告書を出版した1。JRCは2015年以来、バイオエネルギーの需給分析や持続可能性の問題に取り組んできたが、2020年5月のEU生物多様性戦略の策定を受け、エネルギー利用と生物多様性保全を両立させる方策を見出すために本レポートを作成した。IPCC報告書の主執筆者を努めてきたGrassi氏など、10名の専門家が執筆を担当している。
現在、木質バイオエネルギーについて、「カーボンニュートラルではない」「炭素の負債が発生している」「化石燃料よりも環境に悪い」といった批判が、科学者やNGOなどから上がり、欧州でも大きな論争を巻き起こしている2。一方で、温室効果ガス(GHG)の削減効果の評価を含む持続可能性基準の運用などにより、気候変動に資する利用は可能だという主張3もあり、その議論は平行線をたどっている。このような中で、JRCは「科学と政策のインターフェース」という立場から、「議論の無毒化(de-toxify)」という難しい課題に意欲的に取り組んだと言える。
様々なデータを組み合わせた分析により、2000年以降の過去20年間のEUにおける木質バイオエネルギーの利用の内訳は、約5割が工業残渣・廃材、37%が森林から直接収集されたものであると推計している。森林からの直接収集については、全体の17%が枝条や梢端などの林地残材である。残りの20%は丸太に分類されるが、この少なくとも半分は、南欧における伝統的な薪炭林施業4であるとしている。また、嵐や火災、虫害などの自然撹乱後のサルベージ・ロギング5が増加したことで、大量の低質材が市場に供給され、エネルギー利用された可能性も指摘されている。
第5章では、今後EUの森林からのバイオマス利用を増やすためのオプションとして、①残材利用の増加、②植林、③天然林の人工林化の3つの類型を想定し、シナリオを分析している。3つの類型はさらに24のシナリオに細分化され、気候変動と生物多様性の両方の点から評価が行われた。なお、他の環境指標や社会・経済的な効果は考察の対象外となっている。
分析の結果、気候変動と生物多様性保全の両方の点で効果がある(Win-winとなりうる)ものとして、地域条件の範囲内での残材の収穫、耕作放棄地の森林化(混交林もしくは天然更新林)など5つオプションが示されている。反対に他のオプションは、どちらか一方の効果が期待できないか、天然林の人工林化などは両方にとって負の効果があると分類されている。日本のバイオエネルギー利用もこれまでは廃棄物・残材の利用を中心に発展してきたが、今後森林からの直接的な利用を増やす場合は、こうした分析を参考に慎重に検討される必要がある。
しかし、本レポートが森林バイオエネルギーの持続可能性の問題を「やっかいな問題(Wicked-problem)」と位置づけたことにより、建設的な議論に道が開かれることが期待される。Wicked-problemとは、日本語では「やっかいな問題」もしくは「意地悪な問題」と訳される。「解決策を立案するまで『何が問題なのか』すら理解することができない問題」と定義づけられるような、利害関係が複雑で、簡単に答えを出すことができない問題のことを言う。通常の科学的な研究は、条件や前提が整理された「飼いならされた」問題を解くために発展してきたため、「やっかいな問題」の解決に不向きであるとされる。
実は筆者も、森林バイオエネルギー利用のGHG削減効果や炭素会計の問題について、いくつもの科学論文を読んできたが、同じことを考えていた9。つまり、前提の置き方や採用する指標によって、その範囲内であれば「科学的に正しい」結論がいくらでも導けてしまうのである。JRCのレポートにおいても「両方の利害関係者が『科学的には〜なことは明らかだ』と主張している(P83)」と書かれている。
こうした「やっかいな問題」は現代社会では様々な場面で現れることが知られており、その対応策として「順応的、参加型、学際的アプローチ」に基づく協働戦略が推奨されている10。ただし、このようなアプローチの前提として、データ整備とその透明性の確保、またオープンで参加型のプロセスなどが必要である。日本の状況に照らし合わせれば、国産・輸入を問わず、FITにおける燃料使用量や由来などデータの整備や公開、政策形成プロセスへの多様なステークホルダーの参加などが重要になろう。
気候変動枠組条約では、全ての伐採はその時点で、土地利用部門 で炭素排出と計上されているため、エネルギー利用部門における炭素の排出は、二重計上を防ぐためにゼロとみなされている。ただし、バイオエネルギー利用に働いているエネルギー利用部門のインセンティブは、伐採量、つまり土地利用部門からの排出量を増やすというミスマッチを起こす可能性がある。そのため、二つの部門の政策が相乗効果を発揮し、森林の適切な経営により、森林生態系への炭素蓄積量を増やしつつ、伐採した木材を、化石燃料だけではなく、鉄やプラスチックやセメントなどエネルギー他消費型の素材の代替として使うことで、気候変動の対策効果を最大化できるよう、政策的な枠組みを発展させていく必要がある。
現在、木質バイオエネルギーについて、「カーボンニュートラルではない」「炭素の負債が発生している」「化石燃料よりも環境に悪い」といった批判が、科学者やNGOなどから上がり、欧州でも大きな論争を巻き起こしている2。一方で、温室効果ガス(GHG)の削減効果の評価を含む持続可能性基準の運用などにより、気候変動に資する利用は可能だという主張3もあり、その議論は平行線をたどっている。このような中で、JRCは「科学と政策のインターフェース」という立場から、「議論の無毒化(de-toxify)」という難しい課題に意欲的に取り組んだと言える。
森林からの利用を増やす方策は慎重に検討される必要がある
レポートは全部で5つの章から構成されている。第1章の導入の後、第2章から第4章までは、これまでのEUでの木質バイオエネルギー利用の実態と森林現況の記述にあてられている。様々なデータを組み合わせた分析により、2000年以降の過去20年間のEUにおける木質バイオエネルギーの利用の内訳は、約5割が工業残渣・廃材、37%が森林から直接収集されたものであると推計している。森林からの直接収集については、全体の17%が枝条や梢端などの林地残材である。残りの20%は丸太に分類されるが、この少なくとも半分は、南欧における伝統的な薪炭林施業4であるとしている。また、嵐や火災、虫害などの自然撹乱後のサルベージ・ロギング5が増加したことで、大量の低質材が市場に供給され、エネルギー利用された可能性も指摘されている。
第5章では、今後EUの森林からのバイオマス利用を増やすためのオプションとして、①残材利用の増加、②植林、③天然林の人工林化の3つの類型を想定し、シナリオを分析している。3つの類型はさらに24のシナリオに細分化され、気候変動と生物多様性の両方の点から評価が行われた。なお、他の環境指標や社会・経済的な効果は考察の対象外となっている。
分析の結果、気候変動と生物多様性保全の両方の点で効果がある(Win-winとなりうる)ものとして、地域条件の範囲内での残材の収穫、耕作放棄地の森林化(混交林もしくは天然更新林)など5つオプションが示されている。反対に他のオプションは、どちらか一方の効果が期待できないか、天然林の人工林化などは両方にとって負の効果があると分類されている。日本のバイオエネルギー利用もこれまでは廃棄物・残材の利用を中心に発展してきたが、今後森林からの直接的な利用を増やす場合は、こうした分析を参考に慎重に検討される必要がある。
「やっかいな問題」として森林バイオエネルギーの持続可能性を考える
EUのバイオエネルギーの持続可能性確保の政策や規制については、JRCのレポートはいくつかの提案を行いつつも、基本的には肯定的に評価している6。このように、EUの政策に対する肯定的なレポートが出てことに対して、業界団体からは歓迎の声が上がっている7。その一方で、NGOからはEUの規制強化を求める声明が出されている8。執筆陣が企図したように、議論が「無毒化(de-toxify)」されるかは、現時点では判断が難しい。しかし、本レポートが森林バイオエネルギーの持続可能性の問題を「やっかいな問題(Wicked-problem)」と位置づけたことにより、建設的な議論に道が開かれることが期待される。Wicked-problemとは、日本語では「やっかいな問題」もしくは「意地悪な問題」と訳される。「解決策を立案するまで『何が問題なのか』すら理解することができない問題」と定義づけられるような、利害関係が複雑で、簡単に答えを出すことができない問題のことを言う。通常の科学的な研究は、条件や前提が整理された「飼いならされた」問題を解くために発展してきたため、「やっかいな問題」の解決に不向きであるとされる。
実は筆者も、森林バイオエネルギー利用のGHG削減効果や炭素会計の問題について、いくつもの科学論文を読んできたが、同じことを考えていた9。つまり、前提の置き方や採用する指標によって、その範囲内であれば「科学的に正しい」結論がいくらでも導けてしまうのである。JRCのレポートにおいても「両方の利害関係者が『科学的には〜なことは明らかだ』と主張している(P83)」と書かれている。
こうした「やっかいな問題」は現代社会では様々な場面で現れることが知られており、その対応策として「順応的、参加型、学際的アプローチ」に基づく協働戦略が推奨されている10。ただし、このようなアプローチの前提として、データ整備とその透明性の確保、またオープンで参加型のプロセスなどが必要である。日本の状況に照らし合わせれば、国産・輸入を問わず、FITにおける燃料使用量や由来などデータの整備や公開、政策形成プロセスへの多様なステークホルダーの参加などが重要になろう。
バイオエネルギー政策と森林政策との融合による気候変動対策効果の最大化
加えてレポートは、バイオエネルギーの生産に関わるエネルギー政策と、炭素の吸収・固定や生物多様性の保全に関わる森林政策との統合を進めていくことの重要性を指摘している。具体的には、バイオエネルギー利用の「カーボンニュートラル概念」を担保している、森林などの生態系の炭素吸収・固定能力が損なわれないことの前提を改めて確認する必要がある11。世界では、Land-based solutionやNature-based solutionといった言葉で、森林などの生態系の機能を、気候変動対策に組み込むための方策が模索されている。さらには2050年の脱酸素化を目指し、BECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage)などの言葉が踊るようになり、生態系の炭素固定機能は今後ますます重要になる。気候変動枠組条約では、全ての伐採はその時点で、土地利用部門 で炭素排出と計上されているため、エネルギー利用部門における炭素の排出は、二重計上を防ぐためにゼロとみなされている。ただし、バイオエネルギー利用に働いているエネルギー利用部門のインセンティブは、伐採量、つまり土地利用部門からの排出量を増やすというミスマッチを起こす可能性がある。そのため、二つの部門の政策が相乗効果を発揮し、森林の適切な経営により、森林生態系への炭素蓄積量を増やしつつ、伐採した木材を、化石燃料だけではなく、鉄やプラスチックやセメントなどエネルギー他消費型の素材の代替として使うことで、気候変動の対策効果を最大化できるよう、政策的な枠組みを発展させていく必要がある。
- 1JRC (2021) The use of woody biomass for energy production in the EU:2021年2月19日確認
- 2EASAC (2018) Commentary on Forest Bioenergy and Carbon Neutrality:2021年2月19日確認
- 3IEA Bioenergy (2021) Campaigns questioning the use of woody biomass for energy are missing key facts:2021年2月19日確認
- 4天然の萌芽更新によるものであり、日本の伝統的な里山林もこの方法により維持・更新されていた。
- 5風倒や山火事などの自然撹乱が生じた後の林地において、倒れたり枯死した樹木を伐採し、搬出する作業のこと。林地に放置して病害虫を誘引することを防ぐために行われるが、生態系の多様性の向上といった観点から、その必要性についてはしばしば論争になっていることも確かである。
- 6本レポートの主題は、EUの森林からのバイオマス燃料の増産の影響を考察することであり、また最大のバイオマス輸入国であるイギリスのEU離脱もあり、輸入バイオマスの問題についての議論は最小限に留められている点には注意が必要である。
- 7Bioenergy Europe’s views on the JRC report "The use of woody biomass for energy production in the EU":2021年2月19日確認
- 8WWF Europe: Most forest biomass harms climate, biodiversity, or both-EU Commission:2021年2月19日確認
- 9相川高信(2021)「炭素負債をめぐる国際的な議論の動向と日本のエネルギー政策への示唆」第16回バイオマス科学会議発表論文集. 31-32.
- 10Wang (2013) Working with wicked problems in socio-ecological systems: Awareness, acceptance, and adaptation, Landscape & Urban Planning, 110, 1–3.
- 11自然エネルギー財団(2020)「木質バイオエネルギーの持続可能性について 温室効果ガス削減に資する持続可能性確保の制度化」