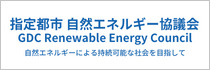はじまりに寄せて
東京電力福島第一原子力発電所の事故からもうすぐ10年を迎える。隣接する原子炉3基が燃料溶融を起こすという未曾有の原発事故であり、その後のさまざまな検証によれば、発生から数週間にわたって世界全体が固唾をのんで見守ったこの事故は、いくつかの偶然の重なりによって、かろうじて最悪の事態を免れることができたものだった。
福島原発事故で放出された放射性物質は、1986年に旧ソ連で起きたチェルノブイリ事故で放出された放射性物質の10分の1から5分の1だとされる1。これら放射性物質は、核種や濃淡に差はあるものの日本の広範囲に飛散した。政府の調査によれば、被曝線量が年1ミリシーベルト(mSv)以上に汚染された地域は、福島県とその近隣都県のみで日本の総面積の約3.4%におよんだ2。1mSvは、一般公衆の年間実効線量限度として定められている数値であり、チェルノブイリ事故の場合では「移住する権利」が適応されるレベルである。放射線には県境はないが、こうした調査は地域単位で行われることが常であり、日本の他の地域のホットスポットについては、測定調査をし偶々発見されなければわからない。また、原発事故の影響で福島県内外に避難せざるを得なかった人は当時少なくとも16万4千人以上にのぼるが、事故から10年を迎える今でも未だ4万人近くが避難をしたままである。そしてこれら数値には、原発事故を理由に福島県以外から他へ避難した人や自主的に避難した人たちはカウントされていない。
まだ事故は終わっていない。事故で放出された放射線が、人々や生物や環境に与えている影響について、調査も論争も続いている。放出された放射性物質の総量や汚染された土地の面積について複数の公的機関でも相違がある。原発事故により避難した人の正確な数値が分からない。次々に増加する汚染水も汚染土も、最終的にどう処分できるか決まっていない。これらすべてが、今も事故が終わっていないことの左証である。なにより、壊れた炉内に溶け落ちた溶融燃料の取り出しも始まっていないが、政府と東京電力は、2050年頃に事故炉の廃炉が終わる目標を掲げている。
かつて福島県知事を務め、国の原子力政策に疑義を申し立ててきた佐藤栄佐久氏は、原発事故以前、政府は「ブルドーザーのように」原子力政策を進めていくと表現した。事故は、そうした政策の行われ方に起因するものであったが、その後10年かけて行われた、小売自由化、発送電分離などの電力システム改革は、果たして、2011年に皆が「変えなくてはならない」と想像していたような未来にたどり着いているだろうか。未だ消費者が自然エネルギーを選ぶための電源表示も義務づけされず、電源トラッキング制度もないし、福島原発事故の処理費用や原発の廃炉費用が託送料金にのせられたり不透明なことが多い。昨年の容量市場を巡るドタバタや年末年始にかけての電力市場の価格高騰も、まだまだ日本の電力市場が未熟で、枠にはめられたままのような不自由さを感じる。
自然エネルギー拡大については、2012年からの8年間で、水力以外の自然エネルギーが発電に占める割合が約1%から10%超えと大きく成長するなど一定の成果を得ているが、世界と比べてのコスト差や解消されない系統や市場の問題など、これから向かうべき100%自然エネルギーへの課題は大きい。
世界のこの10年は、太陽光コストが9割低下したことが象徴するように、まさに自然エネルギー革命が政治や経済まで変容させたものだった。2015年にはパリ協定が締結され翌年発効されるなど、加速する気候危機への警告と対策を求める声が拡がった。コロナ危機に際しても、欧米は、自然エネルギーは脱炭素政策であると同時に新しい経済復興の道筋であるとして、「グリーン復興」に邁進している。日本にしても旧来型のエネルギー政策に再び投資する機会も資金もない。
そうして、これまでの供給側からの一方通行の政策ではなく、需要側からのエネルギー転換の動きも生まれている。国際的著名企業が次々と自然エネルギー100%への転換を宣言し、日本でも多くの企業がその動きに参加している。当財団がWWFジャパン・CDPジャパンと事務局を務める「気候変動イニシアチブ」の動きも活発化し、2018年に105団体からスタートしたネットワークは、550以上に成長した。今や、日本でも、企業の求める規制改革の1位と2位は、今後のエネルギー政策の両輪であるデジタル化と自然エネルギー拡大である。
だが、昨年10月に菅義偉総理が「2050年脱炭素宣言」を行って以来、未だにやっぱり原子力が必要だ、火力にも頼らざるを得ないという声もちらほらある。実際、日本の2050年のグリーン成長戦略では、自然エネルギーは、先進各国の2030年目標と同じ50−60%で、残りは原子力と火力+CCS、水素アンモニアで賄うという。またぞろ同じ道を歩むのか、スタートラインから逆走してしまったように思えてならない。
この10年の日本の歩みを、識者の方々のコラムで振り返り、わたしたちの来し方行く末を見渡していきたいと思う。
東京電力福島第一原子力発電所の事故からもうすぐ10年を迎える。隣接する原子炉3基が燃料溶融を起こすという未曾有の原発事故であり、その後のさまざまな検証によれば、発生から数週間にわたって世界全体が固唾をのんで見守ったこの事故は、いくつかの偶然の重なりによって、かろうじて最悪の事態を免れることができたものだった。
福島原発事故で放出された放射性物質は、1986年に旧ソ連で起きたチェルノブイリ事故で放出された放射性物質の10分の1から5分の1だとされる1。これら放射性物質は、核種や濃淡に差はあるものの日本の広範囲に飛散した。政府の調査によれば、被曝線量が年1ミリシーベルト(mSv)以上に汚染された地域は、福島県とその近隣都県のみで日本の総面積の約3.4%におよんだ2。1mSvは、一般公衆の年間実効線量限度として定められている数値であり、チェルノブイリ事故の場合では「移住する権利」が適応されるレベルである。放射線には県境はないが、こうした調査は地域単位で行われることが常であり、日本の他の地域のホットスポットについては、測定調査をし偶々発見されなければわからない。また、原発事故の影響で福島県内外に避難せざるを得なかった人は当時少なくとも16万4千人以上にのぼるが、事故から10年を迎える今でも未だ4万人近くが避難をしたままである。そしてこれら数値には、原発事故を理由に福島県以外から他へ避難した人や自主的に避難した人たちはカウントされていない。
まだ事故は終わっていない。事故で放出された放射線が、人々や生物や環境に与えている影響について、調査も論争も続いている。放出された放射性物質の総量や汚染された土地の面積について複数の公的機関でも相違がある。原発事故により避難した人の正確な数値が分からない。次々に増加する汚染水も汚染土も、最終的にどう処分できるか決まっていない。これらすべてが、今も事故が終わっていないことの左証である。なにより、壊れた炉内に溶け落ちた溶融燃料の取り出しも始まっていないが、政府と東京電力は、2050年頃に事故炉の廃炉が終わる目標を掲げている。
かつて福島県知事を務め、国の原子力政策に疑義を申し立ててきた佐藤栄佐久氏は、原発事故以前、政府は「ブルドーザーのように」原子力政策を進めていくと表現した。事故は、そうした政策の行われ方に起因するものであったが、その後10年かけて行われた、小売自由化、発送電分離などの電力システム改革は、果たして、2011年に皆が「変えなくてはならない」と想像していたような未来にたどり着いているだろうか。未だ消費者が自然エネルギーを選ぶための電源表示も義務づけされず、電源トラッキング制度もないし、福島原発事故の処理費用や原発の廃炉費用が託送料金にのせられたり不透明なことが多い。昨年の容量市場を巡るドタバタや年末年始にかけての電力市場の価格高騰も、まだまだ日本の電力市場が未熟で、枠にはめられたままのような不自由さを感じる。
自然エネルギー拡大については、2012年からの8年間で、水力以外の自然エネルギーが発電に占める割合が約1%から10%超えと大きく成長するなど一定の成果を得ているが、世界と比べてのコスト差や解消されない系統や市場の問題など、これから向かうべき100%自然エネルギーへの課題は大きい。
世界のこの10年は、太陽光コストが9割低下したことが象徴するように、まさに自然エネルギー革命が政治や経済まで変容させたものだった。2015年にはパリ協定が締結され翌年発効されるなど、加速する気候危機への警告と対策を求める声が拡がった。コロナ危機に際しても、欧米は、自然エネルギーは脱炭素政策であると同時に新しい経済復興の道筋であるとして、「グリーン復興」に邁進している。日本にしても旧来型のエネルギー政策に再び投資する機会も資金もない。
そうして、これまでの供給側からの一方通行の政策ではなく、需要側からのエネルギー転換の動きも生まれている。国際的著名企業が次々と自然エネルギー100%への転換を宣言し、日本でも多くの企業がその動きに参加している。当財団がWWFジャパン・CDPジャパンと事務局を務める「気候変動イニシアチブ」の動きも活発化し、2018年に105団体からスタートしたネットワークは、550以上に成長した。今や、日本でも、企業の求める規制改革の1位と2位は、今後のエネルギー政策の両輪であるデジタル化と自然エネルギー拡大である。
だが、昨年10月に菅義偉総理が「2050年脱炭素宣言」を行って以来、未だにやっぱり原子力が必要だ、火力にも頼らざるを得ないという声もちらほらある。実際、日本の2050年のグリーン成長戦略では、自然エネルギーは、先進各国の2030年目標と同じ50−60%で、残りは原子力と火力+CCS、水素アンモニアで賄うという。またぞろ同じ道を歩むのか、スタートラインから逆走してしまったように思えてならない。
この10年の日本の歩みを、識者の方々のコラムで振り返り、わたしたちの来し方行く末を見渡していきたいと思う。
- 1原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)が2013年に出した報告「電離放射線の線源、影響およびリスクーUNSCEAR 2013年報告書」は、大気放出総量でみるとチェルノブイリ原発事故が11,000ペタベクレル(PBq)、福島第一原発事故が7,500ペタベクレル(PBq)で、福島原発事故による放射性物質の大気放出量総量はチェルノブイリの70%だったとしている。これはキセノン133などの希ガスの放出量が多かった(チェルノブイリの1.1倍)ことに起因しているが、ヨウ素131は7%、セシウム134は20%、セシウム137では大体10%としている。一方で日本の環境省がとりまとめている「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成30年度版)」では、福島原発事故はキセノン133の放出量がチェルノブイリ事故の2倍近くであり、ヨウ素131放出量は7%だが、セシウム134は38%、セシウム137は18%と、UNSCEARに比べ高い値をとっている。
- 2文部科学省は、地表面から1m高での空間線量率について航空機モニタリング調査を実施している(「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング結果(事故直後のデータ)」)。こうしたデータから計算を行うと、8都県で約13,000平方キロにおよぶ土地が、年間実効線量の1mSv以上の汚染を受けていた(「年1ミリシーベルト超す汚染、8都県で国土の3%」、朝日新聞、2011年10月11日)
[特設ページ] 福島第一原子力発電所事故から10年とこれから