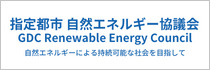政府は2月10日、「GX実現に向けた基本方針(以下、GX基本方針)」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案(以下、GX推進法案)」を閣議決定した。
危機を打開する戦略を提起できていないGX基本方針
GX基本方針は昨年末にGX実行会議がまとめた文書を、殆どそのまま決定したものである。自然エネルギー財団は、昨年12月27日に公表したコメント「GX基本方針は二つの危機への日本の対応を誤る」の中で、その問題点として、(1) 策定プロセス、(2) 原子力発電と化石燃料への固執、(3) 自然エネルギー開発加速への決意の欠落、(4) カーボンプライシング構想の不十分さの4点について具体的な指摘を行った。
GX基本方針の欠陥をあらためて包括的に指摘すれば、 それは「今後10年を見据えたロードマップ」と副題をつけながら、エネルギー危機と気候危機を打開する日本の道筋を示すものに全くなりえていないということである。
昨年のG7サミットの首脳コミュニケでは、「2035年までに電力部門の全て、または大部分を脱炭素化する」という目標が合意された。脱炭素社会の実現にむけては、まず電力の脱炭素化を先行して進めることが必要だという事が世界の共通理解となっているからだ。これに加え、ウクライナ侵略をうけて、化石燃料依存を減らすことの緊急性への認識が高まったことも背景にはあるだろう。
しかし、本年、G7のホスト役を務める岸田内閣が決定したGX基本方針には、いかにして2035年までに日本の電力部門の全て、または大部分を脱炭素化するのか、何も書かれていない。
脱炭素化を担えない原子力発電
「脱炭素効果の高い電源」として「最大限活用する」と位置付けた原子力発電に関しては、既存原発について、「原則40年、延長20年」というこれまでのルールを国民的議論や国会の審議もないまま唐突に改め、「一定の停止期間に限り、追加的な延長を認める」という方針を打ち出した。またこれまで封印してきた原発の新増設を進める方針をもりこんだ。
しかし、既存原発の再稼働は岸田政権の目論見どおりに進んだとしても、2030年度に電力の20-22%を供給するという目標には到達しようがない。安全審査への電力会社の対応の遅れ、繰り返えされる電力会社の不祥事、地元自治体の同意の困難、訴訟リスクなどを勘案すれば、2030年度時点の原子力発電による電力供給量はたかだか10%程度にとどまるだろう。
新増設については「次世代革新炉」の開発を喧伝するが、その中で唯一、商用炉の実現をめざす「革新軽水炉」にしても、制作・建設に着手するのは2030年代に入って何年後かになることがロードマップに示されている。「廃炉を決定した原発敷地内での建て替え」という方針も考慮すれば、2030年代はおろか2040年代の実現も見通せない。
結局、原子力発電は日本の脱炭素化の担い手になりうるものではない。
見通しを示せないゼロエミッション火力
岸田政権が脱炭素電源のもう一つのオプションとして売り込みに躍起となっている「ゼロエミッション火力」に関しても、今後10年間の実際の供給可能量は極めて少ない。水素・アンモニア混焼発電は、エネルギー基本計画でも2030年の総発電量の1%しか見込んでいない。グリーン水素を燃料とする発電が2050年段階で一定の役割を果たすことはありうるが、2030年代に大きな役割を果たすものではない。まして現在推進されている石炭への混焼発電は、石炭火力の延命策という批判をまぬかれようがない。CCS付き火力発電にいたっては、「2030年までのCCS事業の開始(CO2の圧入)に向けた事業環境整備」と記載されるだけで、いったいいつから火力発電での実用段階の稼働を目標とするのか、何の記述もない。
自然エネルギーを脱炭素化の中心に
GX基本方針の内容を検討すれば、いっそう明らかになるのは2030年までのCO2大幅削減、G7が合意した2035年の電源脱炭素化を日本で実現するためには、既に実用段階にあり、日本でもコスト低下の進む自然エネルギー電源の導入をより加速する以外にない、という自明の結論である。
実際、他のG7加盟国の自然エネルギーに関する目標や実際の開発動向を見れば、ドイツが2030年80%、2035年100%、イタリアが2030年70%という導入目標を掲げ、カナダは現時点で既に7割近くを供給している。英国は2035年脱炭素化をどのような電源で行うか明確にしていないが、洋上風力発電開発が大規模に進む一方で、現在11基稼働している原子炉のうち10基は2028年までに廃止の予定である。唯一の新設原子炉の建設は既に予定より遅れている。米国では2023年に新設原子炉2基の稼働が見込まれているが、これに続く新設の予定はなく、既存原発の老朽化と廃炉が続く中で、20%程度という現在の原発による電力供給割合が増える見込みはない。結局、フランス以外の5か国においては2035年に自然エネルギーが電力の70%、80%程度、国によってはそれ以上を供給することになると見込まれる。
GX基本方針は「再生可能エネルギーの主力電源化」を掲げ、いくつかの前向きな記述はあるものの、導入目標に関しては2030年度36₋38%という目標から一歩も出ていない。2035年への言及は全くない。
エネルギー政策における「全方位戦略」の誤り
GX基本方針は、「あらゆる可能性を排除せず、利用可能な技術は全て使うとの発想に立つことが我が国のエネルギー政策の基本戦略である」という政府の方針を改めて記載し、再確認している。様々な可能性を追求することは、一般論としては正しい。しかし、2030年、2035年へのエネルギー転換が火急の課題となっている時に、国際的な経験から既に結論が出ている自然エネルギーで大部分の供給を担うという戦略に背を向け、今から10年間も「革新軽水炉」やCCS付き火力などの技術開発や事業開発整備を重点とし、そこに官民の財源や人的資源を投入しようとするのは、二つの危機への日本の対応を誤るものと言わざるを得ない。
ここまで世界の自動車業界をリードしてきた日本の自動車メーカーは、「全方位戦略」の名のもとに経営資源を分散し、世界のEV競争に取り残されようとしている。「あらゆる可能性を排除しない」という岸田政権のエネルギー戦略は、自動車分野の「全方位戦略」の誤りをより大規模に繰り返すことになる。
日本がエネルギー危機、気候危機に立ち向かうためには、自然エネルギーにより2035年の電力供給をG7の他の国々に伍するレベルまで引き上げることを目指し、その実現に必要な具体的な政策、制度の導入、規制改革を早急に進めなければならない。
GX推進法案が基本方針の欠陥を固定化する恐れ
GX基本方針と同日に閣議決定されたGX推進法案では、化石燃料賦課金や排出量取引制度における有償オークションの実施を可能とする条項が初めて盛り込まれている。この点だけに着目すれば、過去20年余、カーボンプライシングの導入に背を向けてきた経済産業省が世界の流れを受け入れざるを得なかったものとして、肯定的に評価することも不可能ではない。しかし、GX基本方針から想定される炭素価格の水準は、IEAが必要とするレベルの10分の1程度と見込まれている。より早期、より包括的に実効性のある炭素価格の実現をめざす必要がある。
この点も含め、法案にはいくつかの点でGX基本方針の欠陥を法制度として固定化してしまうような問題点がある。GX推進法が、目標として掲げる「脱炭素成長型経済構造」への移行に、本当に資するようにするためには、これらの問題点が是正される必要がある。その主な内容を指摘すれば以下の3点があげられる。
経済産業省が主体となる「GX移行推進戦略」の策定プロセスへの懸念
第1は、GX基本方針を具体化する「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」の策定に関してである。第6条では、この戦略の「案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない」とは規定しているものの、「経済産業大臣が策定する」と明記し、経済産業省が策定の主体になることとされている。
これに対し、同じく脱炭素社会実現への戦略である「地球温暖化対策計画」の策定について、「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、「政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画を定めなければならない」と規定し、策定の主体を特定の省庁とはしていない。グリーントランスフォーメーションは、GX基本方針が冒頭にうたうように、「産業革命以来の産業構造・社会構造の大転換」であるはずであり、その戦略の策定を一省庁にゆだねるのは妥当ではない。
また、経済産業大臣が定めるエネルギー基本計画について、エネルギー政策基本法は「関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」という規定をおいている。GX推進法案にはこうした審議会の関与を求める規定はおかれていない。
脱炭素経済社会への移行を実際に担うのは、いうまでもなく広範な企業であり、自治体であり、何よりも国民である。法案の規定を改め開かれた策定プロセスとする必要がある。
政府支援の対象から自然エネルギー開発を除外する恐れ
第2は、GX移行債などによる財源を投入する対象に関してである。第4条は「国の責務」として、「その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入」すると規定している。 条文だけでは、具体的にどのような事業がこの規定に該当するのか明確ではない。しかし、昨年12月14日に開催された「クリーンエネルギー戦略検討合同会合」に経済産業省が提出した資料では、今後10年間の政府支援額約20兆円の対象に再生可能エネルギーを含めていない。
昨年、策定されたEUのREPowerEUプランでも、米国のインフレ抑制法(IRA)でも再生可能エネルギーの開発加速を最大の課題とし支援の対象としている。特にIRAは、ソーラーパネル、風力タービン、バッテリーの国内製造など、既に実用段階に入っている脱炭素エネルギーの拡大、国内生産体制の強化を重点としている。2023年には太陽光発電の導入が29GWにも達し、米国の発電設備新設の半分以上を占めることが予測されるなど、既に足元での変化を引き起こしている。
先に指摘したようにGX基本方針は、「再生可能エネルギーの主力電源化」を標ぼうしながら、原子力発電やゼロエミッション火力の推進に力点をおいている。政府の財政支援が再生可能エネルギーの開発や、その活用に必要な送電網整備を重点とするものとなるよう、条項を修正し運用する必要がある。
更にGX移行債については、その対象に石炭混焼発電やCO2排出量削減に寄与せず、むしろ増加させてしまうグレー水素の利用を含む恐れもある。もしそのようなことになれば、GX移行債はグリーンウオッシュを推進するものと見なされてしまうだろう。
国際標準から乖離した排出量取引制度の固定化
GX基本方針が打ち出した排出量取引制度の構想は、今後10年間、企業の自主参加を前提とする制度となっている。経済産業省自身が、検討会に提出した資料の中で、自主参加では非参加企業と参加企業の間で負担の偏りが生じうる、参加企業間でも公平性に疑義が生じうるなど、その問題点を指摘している。このように公平性が疑われる制度では、そこで売買される排出枠が国際的に削減価値を認められるものにはなりえない。
GX推進法案は国際標準の排出量取引制度には不可欠な、一定基準以上の事業所・事業者の制度への参加を義務付ける規定を置いていないし、対象事業所・事業者の総量削減の規定もない。このままでは、国際標準から乖離した自主的制度を固定化する法律になりかねない。COP27で公表された「国連非国家アクターによるネットゼロ排出宣言に関するハイレベル専門家グループ」の提言は、自主的削減クレジットは企業など非国家主体が排出削減分に計上してはならない、とする基準を決めた。GX基本方針に基づく自主的排出量取引制度の削減クレジットは、国際的には利用を認められないことになる。
また、10年後の2033年から実施を予定する排出枠の有償オークションについても、その対象が狭いという問題がある。法案第2条は有償オークションの対象とする「特定事業者」を電気事業法に定める発電事業者だけに限定している。発電事業者を対象とすることは当然だが、排出削減の実効性を高めるためには、事業者別二酸化炭素排出量の上位を占める鉄鋼業などを対象とすることが可能になるよう、法案の「特定事業者」に含めるべきである。欧州排出量取引制度では、鉄鋼業にも有償オークションを求めるようにする一方で、オークションによる収益を脱炭素製鉄を進めるための支援の財源としている。このように規制と支援を一体的に進めることによって日本の鉄鋼業の脱炭素化を促進し、グリーンスチールが需要の中心となる時代においても日本の鉄鋼メーカーが国際市場で競争力を高めることが可能になる。
自然エネルギーを基盤とする社会へ移行をめざす戦略への転換を
GX基本方針が冒頭に示している「GX に向けた脱炭素投資の成否が、企業・国家の競争力を左右する時代に突入している」、日本の「技術分野を最大限活用し、GXを加速させることは、エネルギーの安定供給につながるとともに、 我が国経済を再び成長軌道へと戻す起爆剤としての可能性も秘めている。」という認識は全く正しい。問題はどのような方向に向け、日本の技術を活用するのか、政府の資源を投入するのか、民間の投資を誘導するのかであり、GX基本方針はその処方箋を誤っている。
太陽光発電は日本が生み育てた技術であったのに、いまは国内の供給体制は国際的な劣位に立たされている。風力発電でも先駆的にビジネスに参入した日本企業の努力は、旧態依然の電力システムの中で成長の芽を奪われてしまった。国の経済戦略が国内外の投資を呼び込み、日本の新たな成長を可能とするためには、その戦略が脱炭素戦略としても国際的な流れに合致した、まっとうなものであることが必要である。
新たに誕生する成長産業も、鉄鋼業に代表される従来からの重化学産業も、脱炭素化のためには安価で大量の自然エネルギーが国内で供給されることを必要としている。
原子力発電と化石燃料への固執から解放され、日本の豊かな自然エネルギー資源を最大限に活用する戦略へと一刻も早く転換しなければならない。
<関連リンク>
[コメント] GX基本方針は二つの危機への日本の対応を誤る:なぜ原子力に固執し、化石燃料への依存を続けるのか(2022年12月27日)