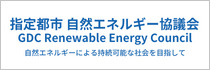公益財団法人 自然エネルギー財団は、本日、アジア各国のエネルギー政策シンクタンク5団体とともに、12月18日に東京において開催されるアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)首脳会合に向けた共同声明を発表しました。
この共同声明は、アジアの豊富な自然エネルギーポテンシャルを活用することで、この地域における今後の高い経済成長を支えるために必要なエネルギーを供給できるという共通の確信を表明し、エネルギー転換の加速に共同して取り組むことを宣言しています。
日本では岸田政権がGX戦略の一環として、アジア・ゼロエミッション共同体構想を推進していますが、その中ではアジアの自然エネルギーポテンシャルの大きさを意図的に覆い隠し、「経済成長の著しいアジア地域は化石燃料の利用を選択せざるを得ない」という宣伝を行っています。政府が推進する石炭アンモニア混焼発電やCCS火力発電は、アジア各国の化石燃料への依存を固定化するものです。
自然エネルギー財団は、アジア各国のシンクタンクとともに、この地域におけるエネルギー転換の道筋を明らかにし、自然エネルギー開発の加速こそが成長と両立する脱炭素戦略であり、この地域の企業にとっても大きなビジネスチャンスを提供するものであることを示していきます。
共同声明・英語(原文)
関連ブリーフィング(報道関係者向け、2023年12月13日)
共同声明全文(参考和訳)
2023年、我々は気候危機の現実を世界各地で目撃し体験した。東南アジアの国々も、この夏、軒並みに過去最高気温を記録し、激烈なサイクロンとそれが引き起こす洪水が大きな被害を引き起こした。
脱炭素エネルギーシステムへの転換は世界共通の課題だが、今後高い経済成長が予測され、2050年までに電力需要が3-6倍に増加すると予測される東南アジアにとっては1、これまでの化石燃料中心のシステムからの転換が喫緊の課題である。
国際エネルギー機関(IEA)、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の研究成果が示すように、東南アジアにはすでに実績もあり、コスト効率の良い自然エネルギーのポテンシャルが潤沢に存在している2。このポテンシャルを適切に活用すれば、大幅にCO2排出を削減できるだけでなく、大気汚染を削減し、エネルギー価格を安定させ、国内エネルギー自給率をあげ、雇用機会を広げることもできる。
いま必要なのは、自然エネルギーによって東南アジアの未来を切り開く明確なビジョンを描き、共有することである。そしてそのビジョンを実現する、各国のエネルギー政策、電力システムの転換を進めることである。
自然エネルギーの豊富なポテンシャルが存在するにもかかわらず、一部の政府や企業は石炭アンモニア混焼発電や炭素貯留固定(CCS)技術付きの火力発電など、化石燃料に依存し続ける、実績のない技術を脱炭素の道筋として主張している3。「クリーン」、「革新的」とも形容されるこれらの技術は、パリ協定の1.5℃目標との整合性、コスト競争力、技術成熟度、環境破壊リスク、ライフサイクル排出量のすべての点において多くの専門家が強い疑念を呈している4。高コストで成熟していないこれらの技術を導入すれば、電力システムの持続可能性と気候目標、エネルギー安全保障に負の影響を及ぼす恐れがある。
私たち、それぞれの国で活動するエネルギー政策シンクタンクは、自然エネルギーの豊かなポテンシャルを十分な根拠に基づき確信すると共に、アジアの未来を形作る上で自然エネルギーが極めて重要な役割を果たすという認識において一致し、連携する。「この地域の自然エネルギーポテンシャルは小さい」という誤解を招く情報が、多くの場合、化石燃料に依存した脱炭素化を推奨する人々によって拡散されている。こうした誤った情報の流布は、アジア地域が有する持続可能な経済成長の潜在能力を分断し、衰退させる。
私たちは日本政府が主催するアジア・ゼロエミッション共同体首脳会議に際し、持続可能なエネルギー政策の展開をアジア全域で実践する、エネルギー転換シンクタンクとして連携していくことを公表する。事実とデータ、そして分析に基づく情報を提供し、アジア地域のエネルギー転換の道筋を提案し、連携してこの地域の持続可能な未来を切り開いていくことをここに約束する。
署名団体:
公益財団法人 自然エネルギー財団
Centre for Policy Dialogue (CPD)
Financial Futures Center (FFC)
Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC)
Institute for Essential Services Reform (IESR)
NEXT group
- 1国際エネルギー機関(IEA)”World Energy Outlook 2022”(2022年10月)、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)”ASEAN Renewable Energy Outlook: Toward a Regional Energy Transformation, 2nd Edition”(2022年9月)、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)・日本エネルギー経済研究所 ”Decarbonization of ASEAN Energy Systems: Optimum Technology Selection Model Analysis up to 2060”(2022年7月)
- 2IEA ”World Energy Outlook 2022”(2022年10月)、IRENA ”ASEAN Renewable Energy Outlook: Toward a Regional Energy Transformation, 2nd Edition”(2022年9月)及びその他の文献によると、2050年におけるアジア地域の電力供給は80~90%が自然エネルギーで賄われるとの記述がある。
- 3経済産業省 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会(第13回)資料3「2030年/2050年を見据えた石油・天然ガス政策の方向性(案)」(2021年2月15日)ほか
- 4日本政府の「第6次エネルギー基本計画」では、2030年までに石炭火力への20%のアンモニア混焼を目指しているが、混焼時のCO2排出量は天然ガス火力の2倍となる。CCS火力については、過去40年間で小規模プロジェクト2件が実現したのみである(出所:Global CCS Institute "GLOBAL STATUS OF CCS 2022", 2022年10月)。 これら2件の回収率は、排出されたCO2の60~70%に留まっている(出所:自然エネルギー財団「CCS火力発電政策の隘路とリスク」2022年4月)。IEEFA “Proposed CCS projects need careful review for cost, technology risks”(2023年5月)も参照。補助金なしの場合、東南アジアの自然エネルギー発電コストはすでにCCSなしの火力発電と競合しており、安い場合もある(出所:BloombergNEF ”Levelized Cost of Electricity 2022 2H”, 2022年12月)。
署名団体(アルファベット順)
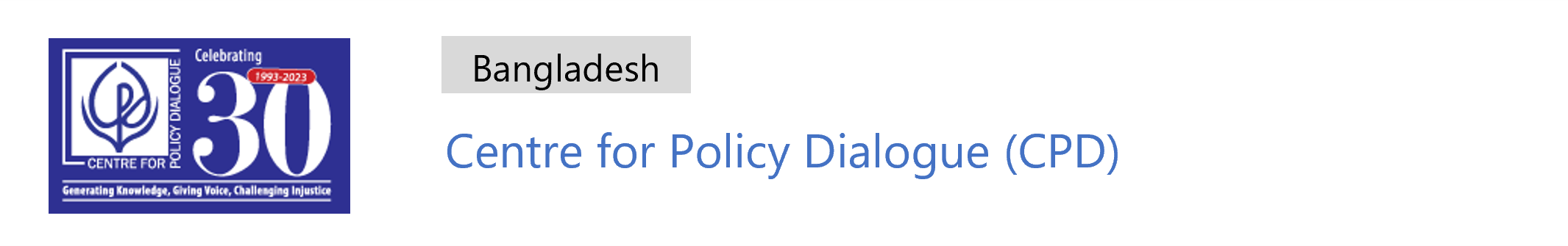

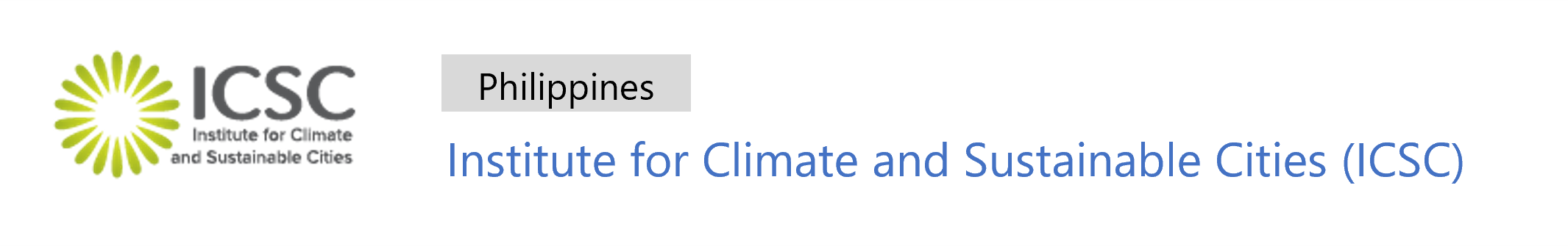

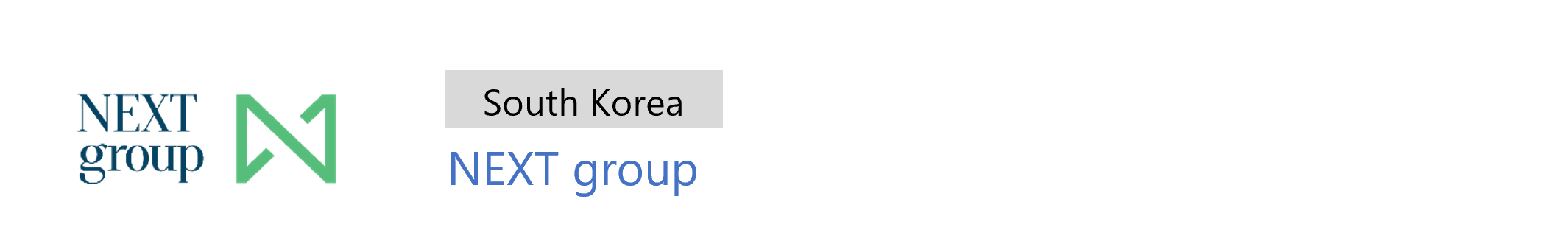
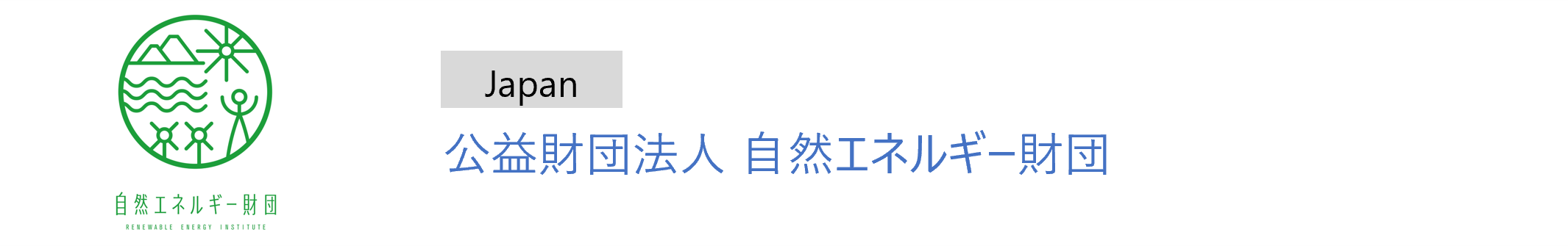
関連ブリーフィング
自然エネルギー財団は、アジア各国のエネルギー政策シンクタンク5団体とともに、共同声明発表にあたり、報道関係者向けのブリーフィングを12月13日にオンラインにて開催しました。このブリーフィングでは各団体代表者からの各国・地域の最新動向の説明に続けてき、記者からの質疑に答えました。
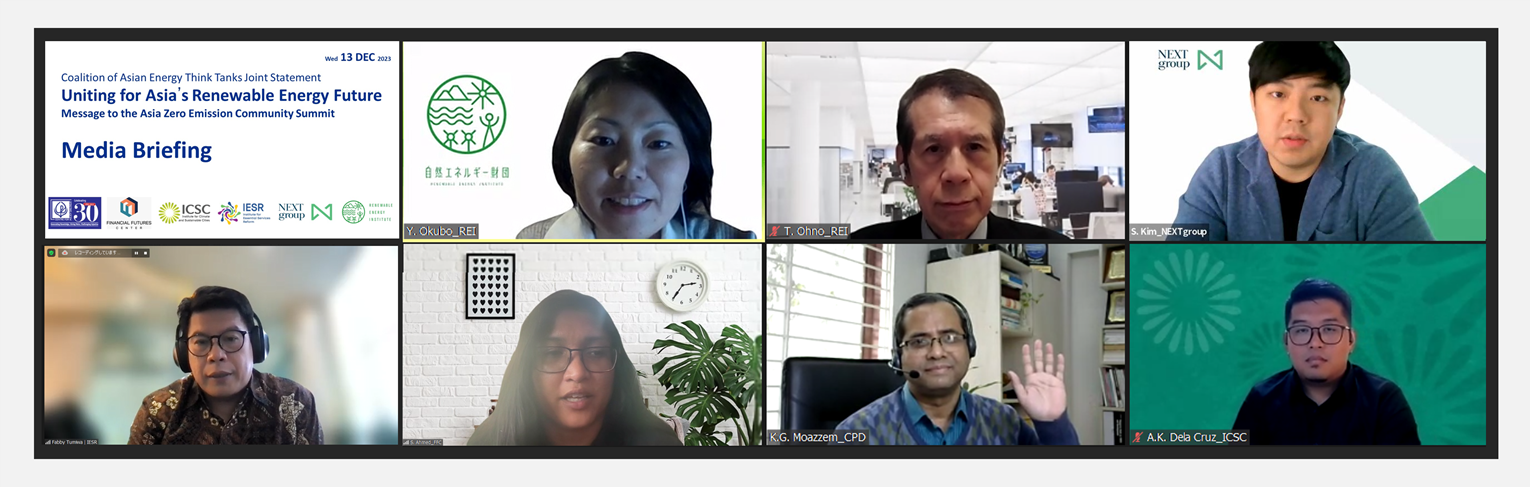
<開催概要>
| 日時 | 2023年12月13日(水) |
|---|---|
| 開催形式 | オンライン ※日英同時通訳あり |
| 主催 | 自然エネルギー財団 |
| スピーカー |
Fabby Tumiwa, Executive Director, Institute for Essential Services Reform (ISER) |