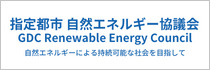要約
「慣性力」「同期化力」のためには火力が必要との議論が行われている。しかし、両方の課題とも、世界では太陽光・風力・蓄電池・高圧直流送電を中心とした(つまり火力発電などが少ない)系統でどう対応するかについて、すでに技術が進展している。本コラムは、「慣性力」「同期化力」の議論を解説し、ブラックボックスになりがちな「慣性力」「同期化力」議論の基礎的理解を目的としている。その上で、世界が気候変動を抑制しながら自然エネルギーによって安定的な電力供給を行うための技術について紹介する。
■ 「慣性力」「同期化力」は、火力発電などの同期発電機 の連系容量が少なくなることによって課題となる場合がある。しかし、太陽光・風力・蓄電池・高圧直流送電(HVDC)がその解決に資するようになってきている。- そもそも、「慣性力」という表現は誤解を招く表現であり、「慣性」などと表現することが適切である。その上で何が課題なのか、どうしたら対応できるかについての正確な議論を理解することが重要である。
- 慣性の議論において問題とされるのは、事故時の周波数の乱れやそこからの周波数回復の問題である。周波数の乱れからの回復が遅くなると、安全措置によって発電機が連鎖的に停止し最悪の事態では停電となる可能性がある。
- 慣性は、連系している同期発電機の運動エネルギーの総量であり、北海道 (50Hz)、北海道を除く東日本(50Hz)、沖縄を除く西日本(60Hz)、沖縄 (60Hz)といった、同じ周波数で同期する系統エリアに対する議論である。各エリアで連系する同期発電機の容量が少ないと慣性は少なくなり、例えば1つの発電機に事故が起こって停止した時の系統周波数の“低下率や“深さ(最低周波数)”が、許容値を超過した場合、問題となる。しかし、太陽光・風力・蓄電池・高圧直流送電が、周波数低下を感知して周波数の低下速度を抑制する「擬似慣性」や、周波数を規定値範囲に制御する「周波数制御機能」のいずれか、もしくは両方を提供することは可能であり、各国で適用されている。
- 「同期化力」は、同期機が並列運転している状態で同期状態を乱す系統擾乱 があった場合に、発電機の出力をタービンの機械的入力と一致する状態に戻そうとする復原力である。自然エネルギー電源など非同期電源の連系量が増えた場合、「同期化力」が少なくなることで周波数安定が維持し難くなるという心配もあるが、太陽光・風力・蓄電池・高圧直流送電の「周波数制御機能」を用いればその心配はほとんど無くなる。
■ 非同期電源の比率が50%程度を超えるような状況に至るまでに、慣性を含めた周波数安定化の議論を行う必要はあるが、現在の日本の非同期電源比率は10%程度である。一方、同期発電機の連系容量が少ないエリアにおいて周波数安定性を高める技術は世界中ですでに実運用されており、火力発電などの同期発電機以外の方法で系統周波数を安定化させる試みは広く行われている。
表1. 慣性と同期化力に関して心配されている事象と対応策の整理

1. はじめに
第7次エネルギー基本計画が、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会において議論されている。2024年7月23日に実施された同分科会の事務局資料に「慣性力としての火力の役割」というスライドが用意され、「太陽光,風力,蓄電池などの非同期電源は、周波数や電流の急激な変化に対して、周波数を維持する機能を持たず」と説明された。その上で、但し書きとして「蓄電池等に疑似的に慣性力を持たせる技術についても開発が進められ、市場投入が始まっているものの、普及拡大はこれからの状況」と記載された(図1)。
図1. 慣性力についての資源エネルギー庁事務局説明資料[1]

また、これとほぼ同じ内容が、例えば、電気事業連合会のWEBサイト[2]などにも掲載されている。そこには、「太陽光発電や風力発電などの再エネは、『非同期電源』と呼ばれるもので、慣性力や同期化力を持っていません。」と記載されている。これらの記載は間違いとまでは言えないが、これまで火力発電などの同期発電機が担ってきた機能(慣性力の提供など)を、他の技術で代替できないというような誤解を与えているように思われる。
そこで、そもそも慣性力とは何のために必要なのか、さらに、慣性力と同時に出てくる同期化力とは何なのか、本稿で整理する。
2. 慣性力とは
電力分野において議論される「慣性力」は、辞書等において定義されている慣性力とは異なる。辞書では、「慣性系に対して加速度運動をしている座標系において、物体の運動に現れる見かけ上の力。」などと書かれている。これは、電車が発車する際、吊革を持っていて、後ろ向きに引っ張られる、いわゆるみかけの力を意味する
では、総合資源エネルギー調査会などの議論において「慣性力」として示されているものは何なのか。先に答えを言うと、辞書で書かれている慣性力ではなく、電気工学分野において「慣性」と呼ばれるものを「慣性力」と呼んでいる。電気工学分野では、並列して回転している発電機のトータルの運動エネルギー(慣性定数×定格容量の積:単位はGW・s)を「慣性(inertia:イナーシャ)」と定義し、評価する。具体的には、同期系統エリア全体 に繋がっている同期発電機の50Hz(火力の場合1分間に1500/3000回転)もしくは60Hz(火力の場合1分間に1800/3600回転)で回転する発電機やタービンの運動エネルギーの総量が慣性である。系統全体の慣性を定量的に評価する値として単位慣性定数という概念があるが、これは、同期速度で回転している発電機の入力を急に取り除き、定格容量の出力を保ち続けたとき、その発電機が停止するまでの時間(単位は秒)をいう。
ここで同期発電機が多い場合と少ない場合を模式的に表し、系統慣性を求めてみる。各タービンおよび発電機の大きさや出力によって各発電機の慣性定数は決まるが、一般的に、蒸気タービンはガスタービンより重く大きいため慣性定数も大きくなる。そのような、個別の発電機およびタービンの特性を含めた図2のような状況を想定した場合、図2(左)の系統は15.7[GW・s]の慣性(運動エネルギー)を蓄積し、図2(右)の系統は8.5[GW・s]の慣性(運動エネルギー)を蓄積していることになる。
図2. 系統に連系している同期発電機による慣性の導出

ここで、図2の状況から両方の系統にある700[MW]のタービンが事故で解列することを想定する(図3)。左の系統では3.5[GW・s]分の慣性(運動エネルギー)が瞬時的に失われるが、それは系統全体では23%分に相当する。一方、同じ量の慣性が右の系統でも失われた場合、それは41%が失われることになる。つまり、右側の系統の方が、より多くの割合の慣性(運動エネルギー)が失われたことになるため、系統周波数の低下速度が左側の系統に比べて速くなる(図4)。
この周波数低下速度(変化率)をRoCoF(Rate of Change of Frequncy)と呼び、また、周波数が最も下がる点をFrequency Nadirと呼ぶが、大規模停電を防ぐため、各国においてRoCoFやFrequency Nadirに基準値を設け、そのために必要な慣性を管理することが行われている。すなわち、慣性はFrequency Nadirに至るまでのRoCoFやFrequency Nadirの深さに影響する因子と言える。なお、自然エネルギー財団では2030年の日本において、様々な自然エネルギー導入シナリオを設定し、その場合の系統慣性を求め、事故時のRoCoFやその後の周波数安定について議論するレポートを2019年に公表している [3]。
図3. 系統事故による慣性(運動エネルギー)の喪失

図4. 系統事故が発生した場合の周波数低下の概念図

ところで、伝統的に慣性は同期発電機など回転機械の回転エネルギーとしてでしか蓄えることができなかった。しかし、技術の進展によって、回転エネルギー以外の形で慣性を疑似的に保有し、必要に応じて出力できるようになってきた(図5)。それが、「疑似慣性」や「グリッドフォーミング」と呼ばれる技術である。
図1で示した総合資源エネルギー調査会の事務局資料では、太陽光・風力・蓄電池などは周波数を維持する機能を持たないと記載されているが、疑似慣性を有するパワーコンディショナー(PCS) は、系統事故時により周波数低下を感知した瞬間、自らの発電出力を上げ、系統に有効電力を供給し、RoCoF(周波数低下率)とFrequency Nadir(周波数低下最下点)を抑制する。これにより、調整力が提供する周波数制御機能(一次調整力)および周波数回復制御(二次調整力)が発動するまでの応答遅れをカバーでき、周波数が所定値(50Hz/60Hz)まで回復することとなる。とくに疑似慣性を有するPCSは応答が早く、系統事故発生直後の数秒以内に反応することができるため、図4の「慣性の量が影響を与える時間領域」においてPCS出力を増加させ、結果的にFrequency Nadirに至るまでの時間を短くし、また、深さを抑えることができるのである。
図6はNEDO研究によって行われているグリッドフォーミングPCS(GFM-PCS:系統形成型)の系統事故時の出力変化であるが、周波数低下を感知した瞬間に有効電力の出力を上げていることが読み取れる。NEDO資料では、GFM-PCSが従来型PCSに対して、周波数低下最下点の抑制に有効であることが示されている。なお、アイルランドでは2017年に、蓄電池システムが疑似慣性の提供と周波数制御する実証試験がおこなわれ、すでに実運用されており[5]、同期調相機との組み合わせ制御の実証試験なども行われている[6]。今後、自然エネルギーを基盤とする電力システムには、疑似慣性を有するPCSの導入を検討することが重要となる。
図5. 疑似慣性による系統周波数の維持機能イメージ

図6. 系統事故時におけるグリッドフォーミングPCSによる有効電力出力変化[4]

以上のように、慣性は系統事故後の系統周波数低下の議論において重要であること、非同期電源も技術の進展によって慣性の提供と周波数制御が可能であることを見てきた。今後、自然エネルギーの増加に伴い、同期機による慣性が減少した場合でも、いかに系統周波数を安定化していくのか、そこを重要な論点とすべきである。
余談であるが、筆者らは「慣性力」という言葉遣いに違和感を持っている。国の審議会などで慣例として「慣性力」という言葉で議論が進められてきたため、様々なところで「慣性力」という言葉が通用しているが、この際、あらためて慣性やイナーシャもしくは慣性エネルギーなど、「力」という単語を使わない用語にしてはどうだろうかと考える。というのも、「力」とは、何らかの対象を変化させる作用(単位は[N(ニュートン)])であるが、「慣性力」という言葉はまるで「慣性力」なる力が周波数を維持する作用を行うような誤解を与えているようにも思われる。なお、慣性の単位はエネルギー[J(ジュール)]であり、理工学の世界において力[N]とエネルギー[J]を一緒にして議論することは決してない。その混乱を端的に表しているのが図1の自転車の絵ではないだろうか。
自転車を複数人でこいでいる状況において、同期電源は立て直す力を持つ電源、非同期電源は耐える力を持たない電源と表現されている。図1であれば、自転車の運転手全員が自転車をこぐのを止めた場合、何秒動き続けるのか、というのが単位慣性定数に相当し、自転車が5秒で止まるのか、2秒で止まるのか、1秒で止まるのか、という議論をしているに過ぎない。結局のところ、止まるまでの数秒以内にどうやって他の運転手が頑張って自転車がとまらないようにし、自転車を動かしていくのかが最も重要な議論のはずである。言い換えるならば、慣性とは他の運転手がリカバリーできる猶予を測る一つの指標に過ぎないのである。そして、慣性が少ない場合であっても、系統事故時に周波数を低下させすぎないためにどのような技術を導入していくかということを議論すべきではなかろうか。それにも関わらず、「慣性力」という言葉を使い続ける限り、まるで「慣性力」なる系統に作用する「力」を維持しなければ大停電が起きるというような印象を与えることになるのではないかと心配する。だからこそ、用語についても電気工学の基礎的概念を大切にした議論にすることを提案する。
3. 同期化力とは
非同期電源(例えば、自然エネルギー)の増加は「慣性力」の低下に加え、「同期化力」の減少をもたらすという議論が行われる場合もある。図7に送配電網協議会が示す同期化力の説明を示すが、この図も初見ではわかりづらい。
図7. 同期電源における同期化力の概念図[6]

同期化力とは、同期発電機が並列運転している状態で同期状態を乱す系統擾乱があった場合、同期発電機の出力をタービンからの機械的入力と一致する状態に戻そうとする復原力と定義できる。少し専門分野の領域になるが簡易的に説明すると、ある発電機の出力Pは、同期発電機の内部誘起電圧Eと母線電圧(系統電圧)Vとの相差角(内部相差角)δと送電線リアクタンスXに対してP=EV/Xsinδで示される(図8)。一般に同期発電機はδ(=内部誘起電圧Eと系統電圧Vの位相差)が10°~30°程度で運転されているが、系統事故などにより系統周波数が一時的に低下すると相差角δが広がる方向になる。ここで、同期発電機は、δが90°以内であれば機械的入力を増やさず発電機出力Pを増加させることができる特徴を元々の性質として有している。しかし、相差角δが広がると今度は発電機の回転子に生じる減速トルクが大きくなり、発電機出力を低下させようとする作用が働く。そして結果的に機械的入力と発電機出力が一致しようとする。この一連の作用が同期化力である。ただし、相差角δが90°を超えると、同期化力は無くなり、同期機が発電機状態と電動機状態を繰り返す、いわゆる脱調という現象に至ることになる。
図8. 同期機の内部誘起電圧と系統電圧との関係

以上の同期化力の概念を理解すると、系統周波数が安定している状況では、非同期電源がどれだけ増えていようが、同期発電機の同期化力に対して何か心配する必要がないことがわかる。敢えていうなら、非同期電源が増えた状況においても、太陽光・風力・蓄電池などが系統全体の周波数を安定させるように働けば、同期電源にとっても何の問題もないと言えよう。すなわち、同期化力の議論も系統周波数の安定をいかに図っていくのかという議論に尽きるわけである。
なお、非同期電源による系統周波数の安定化手法としては、例えば欧米の高圧直流送電は、2010年代よりGFM技術を適用し多数の実績がある。また蓄電池システムへのGFM-PCS適用も進められており、アイルランドやオーストラリアでも実績が出ている。日本ではまだNEDOにおいて研究が行われている段階ではあるが、今後、日本においても非同期電源のさらなる導入拡大に向け、系統周波数の安定化を図る機能を持つGFM-PCSの適用が期待されるところである。
4. さいごに
現在議論されている第7次エネルギー基本計画は、2035年以降の日本のエネルギー構造を定めていく極めて重要な議論である。その中で、将来的な課題の一つとして慣性の議論を行うことは重要であるものの、現行の日本の自然エネルギー導入目標において慣性の議論が定量的に必要なのは、北海道など一部地域に限られるだろう。つまり、慣性や同期化力の議論は、中長期的には重要な課題であるが、自然エネルギー電源を中心とした非同期電源による発電量が少ない段階で、議論だけ先行することは首をかしげざるを得ない。筆者らも現在、将来の周波数安定化に向けた議論を行う準備を進めており、定量的な議論を丁寧に行っていきたいと考える。
- 1定常運転状態において,回転速度と誘導起電力の周波数の比が一定である交流発電機(系統の周波数に合わせた回転速度て発電する回転機型の発電機)。
- 2北海道と東北は直流で連系されており、慣性の議論では別エリアとして扱う必要がある。
- 3沖縄は、九州と連系していない独立系統。
- 4電力系統が安定に運転しているなかで、例えば1つの発電機に事故が起こって停止した時、系統事故や負荷の変動等により電圧や潮流・周波数が乱れる現象をいう。
- 5同じ周波数で同期している系統のことを指す。日本では、東日本が50Hz(1秒分間に50サイクル回転)、西日本が60Hz(1秒分間に60サイクル回転)の交流系統である。但し、北海道は高圧直流連系線で接続しているので同じ50Hzでも別系統となる。
- 6PCS(パワーコンディショナー)とは、直流の電気を交流に変換し、家庭用の電気機器などで利用できるようにするための機械。疑似慣性PCSとは、同期発電機の挙動を模擬し、擬似的な慣性を提供するPCS(PCSの出力を増加し周波数の低下率を抑制する)のことで、系統安定化機能として慣性低下の緩和に寄与することが期待される。
■参考文献
- [1] 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(第59回会合)資料1
- [2] 電気事業連合会WEBサイト
- [3] エリアグリッドインターナショナル、自然エネルギー財団「2030年日本における変動型自然エネルギーの大量導入と電力システムの安定性分析」(2019)
- [4] 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発」事業原簿(2022)
■関連資料
[インフォパック]電力品質維持(周波数安定)に関するQ&A:風力・太陽光・蓄電池・HVDCによる周波数制御(2024年9月18日)