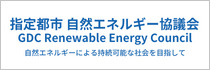基本政策分科会がエネルギー基本計画改正の検討を始めてから、毎回の資料や議論で目立つのは、脱炭素化にむけて原子力発電の重要性を強調する論調である。「脱炭素電源の拡大については、まず原子力の活用が鍵になる」「これからのNDCを考えていく上で、日本にとって非常に重要なのが原子力の問題ではないか」「価格面でも、発電効率の面でも原子力の必要性を痛感する」などなど、原子力の活用を訴える意見が相次いで表明されている。
確かに原子力発電は発電する時点では、CO2を殆ど排出しない。脱炭素電源のひとつとして利用を提唱する意見があるのは不思議ではない。しかし、経済産業省の資料や毎回の議論の中で明らかにされていないのは、原子力発電は、活用するにしても、必要な電力のせいぜい1割しか供給できないという事である。
原子力は3倍化しても電力の1割しか供給できない
5月15日の基本政策分科会で経済産業省はCOP28での脱炭素化をめざす動きを説明する中で、「再エネ3倍・省エネ改善率2倍という取組みとともに、例えば原子力についても3倍宣言というのも出されています。」と説明している。分科会委員の中にはこの説明を受けて「世界は原子力拡大路線になっている」という発言をした人もいる。
原子力3倍化宣言とは、COP28の期間中に日本を含む22カ国が発表した「2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電容量を3倍にする」という共同宣言のことだ。経済産業省は再エネ3 倍、省エネ改善率2倍の目標と並列して説明しているが、再エネ・省エネに関する目標はCOP28の決定文書に盛り込まれた全ての参加国の同意した目標であるのに対し、原子力3倍化は200近いCOP28参加国の中の22か国が賛同した任意の目標にとどまる。
こうした違いを説明しないのはいささか不親切だが、より本質的な問題で説明されていないのは仮に2050年までに世界全体の原子力発電が2020年比で3倍化されたとしても、2050年の電力需要の1割程度しか供給できない、ということである。
国際エネルギー機関(IEA)のネットゼロシナリオでは、2050年の世界の総発電量は2022年の2.6倍に増加し76,838TWhになると想定されている。この中で原子力発電は6,015 TWhであり、割合では7.8%に留まっている(図1)。IEAのシナリオでは、2050年の原子力発電設備容量は916GWとしているが、原子力3倍化が実現できると1239GWになる 。比例的に発電量も増加すると仮定すると8,136TWhになるが、これでも2050年の総発電量の10.6%にすぎない。
22か国の宣言は、2050年までの3倍化を「野心的目標」と表現している。確かに原子炉の新設が低迷する現状からすれば、この目標は野心的だ。しかし、野心的な目標を達成しても必要な電力の1割しか供給できない。
図1 IEA 2050年ネットゼロシナリオの電源構成

日本では電力の1割を供給することも難しい
以上は世界全体の話なので、「いやいや日本では事情は異なる」と言われる方がいるかもしれない。では、経済産業省が7月8日の分科会に提出した資料によって日本の事情を見てみよう。赤の矢印は筆者が追加したもので、現在、稼働している原子炉(図の赤い部分)の設備容量のレベルで引いてある。1000万kW強だ。この線は2055年を過ぎたあたりで図の薄い緑の領域の上を通過する。薄緑の領域は既存の原子炉を最大限活用した場合として国が想定した設備容量を示す。2050年代には現在と同じレベルまで減少してしまうことがわかる。1000万kW強の設備容量で供給できるのは今の電力需要の6%程度である。分科会で盛んに議論されているように2050年にかけて電力需要が増えた場合、例えば、現在の40%増になったとしたら4%程度になる。
しかもここで想定されている設備容量は、現在まだ再稼働の申請すらしていない原子炉、審査中で認可を得らえるかどうかわからない原子炉が全て稼働し、更にまたそれらが60年運転の許可をもらった場合という、相当に楽観的な見通しをした場合の話である。
「だからこそ原子炉の新増設が必要なのだ」という主張が予想される。実際、経済産業省がこの図を示したのは、その議論を意図してのことなのだろう。原子炉の新増設には国の資料によっても20年かかる。気候危機回避に必要な2035年、2040年までの排出削減には間に合わない。放射性廃棄物の処理の目途は依然たっておらず、持続可能な電源とは言えない。
図2 原子力発電の設備容量の見通し

また巨額の建設費を誰が負担するのかという問題がある。新たな電源別発電コストの検討も始まったが、前回の試算で示された原子力発電の11.5円/kWh以上というコストは、泊3号機など日本での最新の原子炉(2005年から2009年に運転開始した原子炉)の建設費を前提にしたものだ。120万kwで4800億円だが、新たな原子炉開発で想定されている革新的軽水炉は、英仏などの実例では、その3~4倍の建設費を要している。巨額の投資を調達して建設する事業者がいるのか、という問題があるし、建設できたとしても発電コストは17~20円/kWh程度という高いものになるだろう。
脱炭素を達成しているべき2050年代に原子力発電で電力の1割を供給するためには、これらの課題を乗り越え、100万kW級の原子炉の建設を今後10年程度の間に10基以上開始しないといけないことになる。ここまでやって、やっと必要な電力の1割を供給できるか、というレベルの話なのだ。残りの9割はどうしたらいいのか。
もっと自然エネルギーの話をしよう
もういちど、図1を見ていただきたい。IEAが2050年の電力供給の最大の担い手としているのは太陽光発電、風力発電を中心とした自然エネルギーだ。89%、約9割を自然エネルギーが供給することをIEAは想定している(ちなみに図ではよくわからないが、CCS付き火力発電は1%、水素・アンモニア発電は2%しか想定されていない)。
脱炭素時代の電力を担うのは、その9割が自然エネルギー発電になるというのは、国際的にはごく常識的な理解になっている、と言っていいのではないか。基本政策分科会の資料や議論を見ていると、この常識が共有されているようには思えない。実際、国が前回の基本計画改正の議論にあわせて作成した「グリーン成長戦略」には2050年でも自然エネルギーは50~60%に留まる、という想定が示されていた。
基本政策分科会で、原子力発電に関する議論が行われることは当然だし、ゼロエミッション火力の議論はあってしかるべきだろう。しかし、脱炭素電源の圧倒的に多くを供給すべき自然エネルギーの拡大のために、どんな政策が必要なのか、もっと時間を割いて議論が尽くされるべきではないか。
これは基本政策分科会の時間配分だけの問題ではない。経済産業省にも環境省にも、あるいは他の省庁でも、太陽光発電、風力発電などの拡大に向け真剣に取り組む多くの職員がいる。しかし、政府全体としてみた時に、自然エネルギー拡大の分野に、脱炭素社会の電源の9割を担う役割にふさわしい規模の人的資源が投入されているのだろうか。
自然エネルギー拡大にむけては、様々な課題がある。しかし地域共生にしても、出力変動への対応にしても、太陽光パネルのリサイクルにしても、既に課題を乗り越える優れた実例が全国で生まれている。そうした実例を集約し、教訓を引き出し、全国に広げるための仕事にこそ、省庁の力を集中すべきだ。
6月から7月にかけて、RE100、気候変動イニシアティブ(JCI)、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)に参加する企業が日本での自然エネルギーの大幅な拡大を求めるメッセージを相次いで公表した。これらの動きの背景にあるのは、日本における自然エネルギー拡大の立ち遅れに対する深刻な危機感である。電力に占める自然エネルギーの割合が欧州全体でも4割を超え、ドイツでは2024年上半期に57%に達する中で、日本での割合は2割強に留まっている。このままでは日本に立地する企業は国際市場での競争で勝ち抜くことができない。これらの企業が求めているのは、自然エネルギーであり原子力発電ではない。