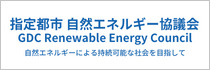いま、国会ではGX推進法改正案に関する審議が行われている。改正案の中心は排出量取引制度、GX-ETSの導入である。GX-ETSは2023年度からボランタリーな制度として施行が始まっていたが、これに対して気候変動イニシアティブ(JCI)などから、制度への参加や削減の履行を義務的なものとして実効性を高めることが提案されてきた。今回の改正案は、これらの声にも応え、一定の制度強化が盛り込まれている。
国における排出量取引制度導入の検討は、環境省が2000年に「排出量取引に係る制度設計検討会」を設置して以来、実に4半世紀に渡って延々と続けられてきた。この間、世界では2005年の欧州排出量取引制度(EU-ETS)を最初に導入が続き、本年1月時点では欧州以外にも北米諸州、中国、韓国などで開始され計38の制度が運用されている。日本でも東京都が2008年に「総量削減義務と排出量取引制度」を条例化し、2010年4月から既に15年の運用実績を有している。
筆者は、東京都の制度導入を担当し、その後、国のいくつかの検討会にも参加してきた。それらの経験や長期間、制度を実施してきた欧州の教訓を踏まえ、提案されているGX-ETSが脱炭素への排出削減に本当に役立つ制度とするために、以下3つの提案を行いたい。
|
これらの提案には、本来、改正法案に活かしてほしい部分もあるが、GX-ETS制度の詳細は、今後制定される実施指針などに委ねられている部分も少なくない。以下に述べる欧州の事例も含め、今後、制度の実効性を高めるための参考になれば幸いである(なお、併せて掲載する参考資料「カーボンプライシングの概況とGX推進法改正法案の課題」もご参照いただきたい)。
提案1 参加企業の排出枠合計の上限値(キャップ)を設定し、国全体の削減目標(NDC)と整合するものにする。
排出量取引制度(以下、ETSと書く)では、制度の対象となる企業(あるいは施設)に各年(複数年の場合もある)の排出が認められる上限量=排出枠が設定される。排出枠の設定は次項で述べるように重要だが、ETSが本当に排出削減に効果がある制度とするために必要なのは、個々の企業の排出枠の総合計である「キャップ」をしっかりと定めることである。このキャップは、導入する国(あるいは地域)全体の削減目標と整合するように設定され、次第に強化されていく。 次第に強化される、つまり小さくなるキャップに基づいて各企業への排出枠も小さくなっていくので、各企業が排出枠の目標を達成すれば、制度全体としても確実に総量削減が実現される。これがETSの最も肝心なポイントである。その意味では「ETS(Emissions Trading System)=排出量取引制度」というネーミングは、制度内容の半分しか表現していない。米国などでは、この制度を「キャップ&トレード制度」と呼び、より制度の趣旨を明確に表現している。 欧州の制度、EU-ETSは2005年に導入されたが、2013~2020年の第3フェーズ、更に2021年からの第4フェーズでキャップが強化されるまでは、十分な排出削減効果を発揮しなかった。その最大の理由は、第1、第2フェーズでは配分された排出枠が過剰であり削減インセンティブが働かなかったためである。図1でわかるように、第1、第2フェーズでは、排出枠および、排出枠として機能する国際クレジットの量が、オレンジ線で示される排出量を上回っていた。
いま国会に上程されている改正案では、企業への排出枠の配分については規定されているが、その総合計がどのように定められるのか、キャップを導入するものになっていない。
本来は法案が修正されるべきだが、次善の策としては、「排出枠の割当てに関する基本的事項」を定めるとしている実施指針(改正案32条)において、キャップを設定すること、またキャップをNDCの削減目標に整合するように段階的に強化していくことを明示的に定めるべきと考える。ちなみに東京都でもキャップは制度の導入を定めた条例(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)本体ではなく、条例に基づく「東京都地球温暖化対策指針」の中で定められており、5年間の削減計画期間ごとに次第に強化されてきている。
提案2 排出枠の配分は、発電事業者だけを有償にするのではなく、段階的に対象企業全体に広げていく。また有償化の時期を前倒ししていく。
制度対象の企業に対する排出枠の配分は、①当該企業の排出実績に応じて配分するグランドファザリング方式、②当該企業の属する業種の標準的な排出原単位に基づいて配分するベンチマーク方式、③企業が自ら必要とする排出枠を市場で調達するオークション方式、の三つがある。①と②は、通常、無償で排出枠が配分されるのに対し、③は有償で配分されるという大きな違いがある。
排出する二酸化炭素の環境負荷に見合った負担を排出企業が負担するという意味では、③のオークションが最も妥当な方式であるが、それまで無償だった二酸化炭素炭素排出をいきなり有償にする、という制度には賛同が得られづらい。このため過去に導入されたETSの多くでは、無償配分から始まり、徐々に有償配分を増やしていくようにしてきた。この意味では、GX-ETSが2026年の制度開始時は、ベンチマーク方式も含めた無償配分で始めることは理解できる。
問題は、改正法案が条文(第34条)の中で特定事業者以外の対象企業に対する排出枠の配分は無償で割り当てると明記してしまっていることである。ここでいう特定事業者とは電気事業法で定める発電事業者の中で排出量が多い者だということも条文(第2条)で定義しているので、この改正法案では、将来的にも大手の発電事業者以外の企業は、有償配分=オークションが適用されないことになってしまう。
EU-ETSでは、2013年からの第3フェーズで発電部門の排出枠を全量オークションによる有償割当にしたことに続き、2021年からの第4フェーズでは海運、産業部門も段階的にオークションとしてきた。2023年の段階では、排出枠全体の約50%が有償割当になっている。欧州委員会の計画では、 第4フェーズ全体では57%が有償割当になる。
国際エネルギー機関(IEA)は、2020年に公表した「効果的なETSの実施」というレポートの中で、排出枠の配分は無償から有償への移行していくべきと指摘し、その理由として、以下3点をあげている。
- ① 無償の排出枠配分にともなって生じうる歪みを是正する。
- ② 排出枠オークションによって、歳入を得ることができる。
- ③ 無償配分は、排出削減効果を弱める。
これらの理由のうち、②について補足すると、EU-ETSでは2023年にオークションによって436億ユーロの歳入を得ている。1ユーロ=160円とすれば、約7兆円となる。EUではこのオークション収入は鉄鋼部門などの脱炭素化に必要な投資を支援する原資となっている。③の排出削減効果の違いについては、実例で見ることができる。図2が示すようにEUでは、先行的に有償オークションが始まった発電部門(燃焼と表記)は他部門より大きな削減が進んできた。
図2 EU-ETSでの排出量削減の推移

かつて排出削減が困難と言われてきた鉄鋼業など重化学工業部門でも、技術開発の進展により脱炭素化への道筋が見えてきている。排出枠の有償配分を発電事業だけに限定する理由はない。むしろ鉄鋼業なども順次、有償オークションに移行し、得られた歳入も活用してこれらの部門の脱炭素化投資を支援するべきではないか。
現在の政府の計画では、発電部門での有償オークションが始まるのは2033年度以降とされている。2030年、2035年への大幅削減が求められている中で、2033年まで先送りするのではなく、前倒しすべきだ。
提案3 炭素価格の上限は、排出削減に効果がある水準になるように設定する。
改正法案は、排出枠価格が高くなりすぎないように、上限価格(参考上限取引価格)を定めるものとしている(39条)。炭素価格に上限、下限価格を設定すること自体は、これまでのETS制度の運用の経験を踏まえ、諸外国でも行われている。
GX-ETSで懸念されるのは、むしろ炭素価格が排出削減に効果があるように十分に高い価格になるかどうかである。EU-ETSでは、第1、第2フェーズのキャップが甘く過剰な排出枠が配分されたため、炭素価格は低迷し、排出削減効果が弱かった。炭素価格は第3フェーズの前半ではまだ4~8ユーロ程度に留まっていたが、2018年から上昇が始まり削減効果が発揮されるようになってきた。2022-2023年にフランスの原子発電所トラブルによる大規模な運転停止などの理由もあり、80ユーロ台に上昇した後、2024年には50-60ユーロ台となっている。
GX-ETSで十分に高い炭素価格になるか懸念される理由の一つは、上述のように、そもそも現在の法案では、キャップの設定が明示されていない点にある。もう一つの理由は、GX-ETSが直接的には排出削減を目的とするものとして設計されていないことである。
EU-ETSの場合は、「危険な気候変動を回避するため科学的に必要と考えられる削減レベルに貢献するよう、温室効果ガスの排出削減量を増加させる」ことが制度目的として明記されている(EU ETS指令第1条)。炭素価格も、制度目的に沿って削減目標の達成に必要な価格水準に設定することがめざされる。
これに対し、政府はGX-ETSの目的に関する説明の中で、あえて諸外国が排出削減を制度目的としていることと対比し、GX-ETSでは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する」ことが制度目的であると述べている。このような前提の下でどのような炭素価格が目指されるのか、これまでの政府の説明では不明確だ。明らかなのは、発電事業者に対する有償オークションで得られる歳入は、別途、導入される化石燃料賦課金とともに、20兆円規模のGX経済移行債の償還財源になる、ということだけである。仮に炭素価格が、20兆円の償還財源を得るためにだけ設定されるなら、排出削減に効果のある十分に高いレベルにはならないだろう。
排出削減に効果のある炭素価格を実現するためには、前述のようにキャップが設定されるべきだが、あわせて、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が1.5℃目標を達成するために必要な炭素価格などを、上限設定にあたって参照にしていくべきだ。
先駆的な企業、自治体の協力を得てGX-ETSを機能する制度へ
ETS導入に向けた政府の取組が世界に大幅に遅れる中で、脱炭素に先駆的に取り組む企業や自治体は、国の動きを待たず、カーボンプライシングの実現を目指してきた。多くの企業がインターナルカーボンプライシングの導入を進め、CDP回答企業(主に東証プライム市場上場企業)のうち、63%はインターナルカーボンプライシングを導入済み、もしくは2年以内に導入予定であるという。自治体では、前述のように東京都が2008年にキャップ&トレード制度を都条例の改正で導入している。隣接する埼玉県も都制度に類似の制度を導入している。
GX-ETSを本当に脱炭素に貢献する制度としていくためには、国はこれらの企業や自治体の先駆的な取り組みに学び、GX-ETSの運用の中でもこれまでの取組の成果を活かせるようにしていくべきだ。間違っても、先行して積み上げられてきた企業・自治体の努力を損なうようなことがあってはならない。
ETSはうまく設計・運用され、タイムリーに改善されていくなら、脱炭素化への強力なツールになる。しかし、運用を誤れば、参加企業に多くのペーパーワークを強いるだけで削減に効果のない制度になってしまうリスクもある。
国が、企業、自治体の協力を得てGX-ETSを脱炭素に機能する制度として発展させていくことを期待したい。