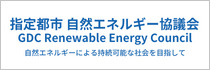日本の3メガバンクを含む大手銀行や生命保険、大手アセットマネジメント会社の多くが、国際的イニシアチブに加盟し、世界の産業革命前からの気温上昇を1.5℃以内に抑えることと整合する投融資行動をとることを宣誓している。これらに加盟している金融機関は、2050年時点のネットゼロに加えて、中期目標も設定し、それを達成することが求められている。
日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言している。一方で、IPCC第六次報告書では、産業革命前からの気温上昇を50%より大きい確率にて1.5℃以内に抑えるには、2035年までに2019年比で温室効果ガス60%、二酸化炭素65%の削減が必要であるとしている。つまり、1.5℃に整合するには、2050年ネットゼロだけでは不十分であり、より早期に大幅な削減を行うことが必要なのである1。
IPCC第6次報告書が示したCO2排出量2035年までに65%減に対して、国際的な批判の高まっている石炭火力へのアンモニア混焼政策は、1.5℃と整合しているのだろうか。答えは「していない」と言わざるを得ない。
石炭火力へのアンモニア混焼政策が1.5℃と整合しない理由を以下にまとめた。
|
国際エネルギー機関ネットゼロシナリオでは、先進国は2030年までに排出削減対策をしていない(unabated)石炭火力を全廃することが示されている。IPCC第六次報告書では排出削減対策済み(abated)となるには90%程度の脱炭素化が基準であるとの記載があり、2030年時点に20%混焼では不十分である。
|
|---|
国際エネルギー機関が2050年までのネットゼロの道筋を示したシナリオ2では、先進国では2030年までに「未対策 (unabated)」石炭火力は廃止することが示されている。では、「対策済み(abated)」とは、どの程度の対策を意味するのだろうか。IPCC第六次報告書には、「対策済み(abated)」とは、90%といった高い吸収率のCCSを入れることを意味することが明記してある3。それに基づいて科学に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi, Science Based initiative)における金融セクター向け化石燃料方針案においても、90%以上を採用している4。
エネルギー基本計画が目標とするのは2030年時点においては石炭火力へのアンモニア20%混焼にすぎない5。「対策済み(abated)」とされる90%には到底及ばない。理論的には、アンモニア混焼に加えて、火力発電所で二酸化炭素回収装置を設置しCCSによる排出削減を行う方法もある。しかし政府のCCS目標は2030年に600~1200万トンの回収・貯留をめざすというものである。100万kWの石炭火力発電所からの二酸化炭素排出量は約500万トンであり、日本には5000万kW以上の石炭火力発電所が存在している。2030年600~1200万トン目標をめざす取組は始まったばかりであり、この中には火力発電だけでなく製鉄や製油、化学工場など様々な分野での回収が含まれる。政府のCCS目標が仮に達成されたとしても、石炭火力発電所の排出削減への貢献は限定的である。
2030年までに「未対策 (unabated)」石炭火力を全廃するためには、アンモニア混焼もCCSも全く有効な対策にならない。すべての石炭火力を廃止する必要が出てくるというのが、論理的な結論となる。
図1は、石炭火力に20%のアンモニアを混焼したとしても、国際的基準である90%以上の削減には全く満たないことを視覚的に明らかにしたものである。50%でも満たないことは明白である。データとしては、文献6に示されている以下の排出原単位を用いた。
- 石炭燃焼時の熱量あたりCO2排出原単位:115g-CO2eq/メガジュール(低位)
- 石炭製造時の熱量あたりCO2排出原単位:8g-CO2 eq /メガジュール(低位)
- 天然ガス起源アンモニアの製造時の熱量あたりCO2排出原単位:112g-CO2 eq /メガジュール(低位)
- 太陽光発電による電力によるアンモニア製造時の熱量あたりCO2排出原単位:13g-CO2 eq /メガジュール(低位)
これらの原単位を元に、①から⑦のケースの「石炭火力専焼」ないしは「石炭火力アンモニア混焼」時のライフサイクルCO2排出量を計算した。IPCC第六次報告書にて「対策済み(abated)」を示すと記載のある“発電時点における90%以上のCCSによるCO2吸収と永続的貯留を行う”ケース②と同等のライフサイクルCO2に収まるには、1) 天然ガスから製造するアンモニアに95%以上のCCSを付けた場合、必要なアンモニア混焼率は88%以上であること(ケース⑥)、2) 太陽光発電の電力を用いて製造するアンモニアを用いる場合、必要なアンモニア混焼率は93%以上であること(ケース⑦)がわかる。そのような製造過程でのCCSによる高い吸収率または低い排出原単位、そして約9割以上という高い混焼率の両方があって初めて、「対策済み(abated)」とみなされる。そうなってくると、わざわざ混焼をする意義が見えにいといえよう。
以下、図1にて示した7つのケースの詳細を示す。繰り返しになるが、IPCC第六次報告書にて示された国際基準に基づくと、②・⑥・⑦のみが「対策済み(abated)」とみなされる。
- ① 石炭100%を燃焼させる場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
- ② 石炭100%を燃焼させ、発電のための燃焼時のCO2排出量の90%をCCSにて吸収した場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
- ③ 石炭80%、アンモニア20%混焼だが、アンモニアについては天然ガスから製造しCCSによる吸収は行わない場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
- ④ 石炭80%、アンモニア20%混焼だが、アンモニアについては天然ガスから製造しCCSによって95%を吸収する場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
- ⑤ 石炭80%、アンモニア20%混焼だが、アンモニアについては太陽光発電の電力を用いて製造する場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
- ⑥ 「対策済み(abated)」の定義である「②」のライフサイクル排出量に一致すべく、石炭火力は燃料の12%とし、製造過程で発生するCO2の95%をCCSにて吸収したアンモニアを88%混焼する場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
- ⑦ 「対策済み(abated)」の定義である「②」のライフサイクル排出量に一致すべく、石炭火力は燃料の7%とし、太陽光発電の電力を用いて製造したアンモニアを93%混焼する場合の熱量あたりライフサイクルCO2排出原単位
図1 石炭火力と天然ガス起源または再エネ起源アンモニア混焼時の
ライフサイクル排出量と「対策済み(abated)」国際標準(赤線)との比較
(縦軸単位:g-CO2eq/メガジュール(低位))7

提案:管理的石炭火力フェイズアウトにこそGX債を活用せよ
石炭火力は混焼によって延命をするのではなく、フェイズアウトに資金を提供する管理的フェイズアウトを進めてはどうか。金融機関による国際イニシアチブの多くが参加するグラスゴーネットゼロ金融同盟(GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero)においても、石炭火力のフェイズアウトに資金を提供することこそ、公正な移行のメインストリームとして、基準を定めている8 ,9 。金融機関向けの科学に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi)要件改訂においても、化石燃料セクターに対して、資金を入れたまま1.5℃に沿ったビジネスへの「移行(トランジション)」をするようにエンゲージメントすることで、通常の目標から控除できることが提案されている10。もちろん、金融SBTとしては、国際エネルギー機関によるネットゼロシナリオを参考に、中高所得国においては2030年までに、それ以外の国においては2040年までに、90%以上のCO2排出量をCCSにて排出していないもの以外は、すべての石炭火力を廃炉にエンゲージメントすることが必須条件となっている。
石炭火力へのアンモニア混焼は、2035年までに電力部門の全て又は大部分を脱炭素化するというG7としての1.5℃の経路に明確に整合していない。無理に延命するために、高コスト11かつ不確実性の高い技術に莫大な資金を投入するのではなく、管理的フェイズアウトの考え方をGX経済移行債にも導入することが、本当の意味で現実的な道なのではないだろうか。そうすることで、石炭火力を現在保有している企業の経営に打撃を与えることなく、金融機関としてもネットゼロに正面から貢献することができ、脱炭素化も大きく進む。
日本には洋上風力を含めた莫大な自然エネルギーのポテンシャルがある12。自然エネルギー財団では、2035年までに電力部門の80%について自然エネルギーによって賄う道を定量的に示している13。洋上風力ポテンシャルは、多くが北海道と東北地方に存在しており、2035年80%の場合は、2050年に50〜60%の現行計画と比べて、早期により大きく系統増強を含めた柔軟性を活用できるようにすることが必要となる14。早急に現実的な2035年目標を設定するとともに、2050年へのロードマップを見直し、今から必要な投資計画を立てる必要がある。そこにこそ、GX経済移行債が活躍するのではないだろうか。
- 12023 年9 月に国際エネルギー機関(IEA)が発表した「Net Zero Roadmap 報告書改訂版」は、気温上昇を 1.5℃までに抑える「ネットゼロ(排出)」達成のためには、2035 年の温室効果ガス排出量を、先進国は 2022 年比 80%減、新興国および開発途上国は同 60%減が必要であり、特に先進国は電力部門からの排出をほぼゼロにすることが求められる、としている。(IEA,” Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach”)
- 2IEA “Net Zero by 2050” (May 2021) (アクセス日:2023年8月17日)
- 3IPCCによるClimate Change 2023 Synthesis Report のSection 4「Near-Term Responses in a Changing Climate」には、” In this context, ‘unabated fossil fuels’ refers to fossil fuels produced and used without interventions that substantially reduce the amount of GHG emitted throughout the life cycle; for example, capturing 90% or more CO2 from power plants, or 50 to 80% of fugitive methane emissions from energy supply.”との記載がある(p.92)。仮訳は以下の通り。「この文脈において「対策していない」化石燃料とは、ライフサイクルを通じて排出される温室効果ガスの量を大幅に削減するような介入を行わずに生産・使用される化石燃料を指す。例えば、発電所から排出されるCO2を90%以上回収することや、エネルギー供給から排出されるメタンガスの50~80%を回収することなどである。」
- 4SBTiが2023年7月に開催した「Deep Dive Webinar on Fossil Fuel Finance Position Paper Consultation Draft」ウェビナー資料 (p.18)によると、対策(abatement)の定義として、直接・間接の排出量が90%以上削減していることを明示している。
- 5株式会社JERAは2030年代半ばに50%以上の混焼を目指すとしている(出典:JERAウェブサイト)が、50%以上の混焼でも90%削減には達しない。
- 6国際エネルギー機関(IEA) “The Role of Low-Carbon Fuels in the Clean Energy Transitions of the Power Sector” (2021年10月) (アクセス日:2023年11月18日)
- 7燃料製造時CO2排出量には、石炭燃料分も含めていることに留意されたい。例えば、ケース③では、a. 発電時CO2排出量(115*80%)、b.燃料製造時CO2排出量(アンモニア分として112*20%、石炭分として8*80%)を足した値としている。
- 8GFANZ “The Managed Phaseout of High-emitting Assets” (June 2022) (アクセス日:2023年8月17日)
- 9Asia-Pacific Network of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, “Financing the Managed Phaseout of Coal-Fired Power Plants in Asia Pacific” (June, 2023) (アクセス日:2023年8月17日)
- 10SBTi “The SBTi Fossil Fuel Finance Position Paper, consultation draft” (June 2023) (アクセス日:2023年8月17日)
- 11BloombergNEF 「日本のアンモニア・石炭混焼の戦略におけるコスト課題」(2022年9月) (アクセス日:2023年8月17日) 本文献では、脱炭素手法として比較した場合、CCSを十分につけて製造したアンモニアを燃焼する火力発電は、蓄電池をつけた太陽光発電よりも、2030年時点でも2倍以上のコストとなる見込みであることが示されている。
- 12自然エネルギー財団「浮体式洋上風力事業化の加速に向けた提言」(2023年11月) (アクセス日:2023年11月26日) 本報告書では、浮体式洋上風力のポテンシャルとして、最大952GWと試算し、送電線・変電所、港湾の有無、事業性の観点から10ヶ所の有望海域を提案しているほか、商業規模の浮体式洋上風力を早期運転開始する―ファストトラック(Fast Track)を提案している。
- 13自然エネルギー財団「2035年エネルギーミックスへの提案(第1版)自然エネルギーによる電力脱炭素化を目指して」(2023年4月) (アクセス日:2023年8月18日)
- 14自然エネルギー財団「2050:自然エネルギーによる脱炭素化のための送電網のあり方」(2023年4月) (アクセス日:2023年11月19日)